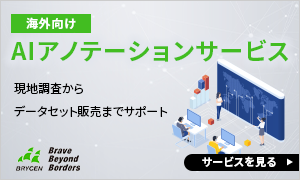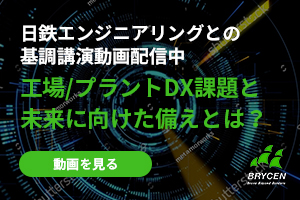データエンジニアリングとデータサイエンスの違いや関係性について解説
2025.11.10

データを活用したビジネス推進において、データエンジニアリングとデータサイエンスという言葉をよく耳にするようになりました。どちらもデータを扱う専門分野ですが、その役割や目的は大きく異なります。 しかし、これらの違いを正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。データエンジニアリングとデータサイエンスは、それぞれ異なる専門性を持ちながらも、互いに補完し合う重要な関係にあります。今回は、両者の概要から具体的な違い、関係性、そして活躍する分野まで詳しくご紹介します。ぜひデータ活用の推進や人材育成の参考にしてください。
データエンジニアリングとデータサイエンスの概要
データエンジニアリングとは、データを収集し、整理し、活用できる状態に整える技術分野のことを指します。膨大なデータを効率的に管理するためのデータ基盤を構築し、データの品質を維持しながら、必要な時に必要な形でデータを取り出せる仕組みを作ることが主な役割です。
データエンジニアは、データベースの設計や構築、データの取得と変換処理、データパイプラインの構築などを担当します。データが円滑に流れるインフラを整備することで、組織全体がデータを活用できる環境を提供します。
一方、データサイエンスとは、データから価値ある知見を引き出し、ビジネス課題の解決や意思決定を支援する技術分野です。統計学や機械学習の手法を用いてデータを分析し、パターンを発見したり、将来の予測を行ったりします。
データサイエンティストは、ビジネス課題を理解した上で、適切な分析手法を選択し、データから実用的な答えを導き出します。分析結果をわかりやすく可視化し、経営層や関係部署に提示することで、データに基づいた意思決定を促進します。このように、両者はデータを扱う点では共通していますが、その目的と役割は明確に異なっています。
データエンジニアリングとデータサイエンスの4つの違い
データエンジニアリングとデータサイエンスには、主に4つの観点で違いがあります。ここでは具体的な違いを詳しくご紹介します。
・メインとなる仕事内容
・必要とされるスキルと専門知識
・成果物と評価指標
・業務における視点と思考方法
メインとなる仕事内容
データエンジニアリングの仕事内容は、データ基盤の構築と維持管理が中心です。さまざまなデータソースからデータを収集し、整形して保存するデータパイプラインを構築します。また、データベースの設計や最適化、データの品質管理、システムの監視と運用保守なども担当します。
具体的には、顧客管理システムや販売システムなど、複数のシステムから発生するデータを統合し、分析しやすい形に整えます。データの取得頻度や処理速度、保存容量などを考慮しながら、効率的なデータ基盤を設計する必要があります。
一方、データサイエンスの仕事内容は、データ分析と課題解決が中心です。ビジネス課題を理解し、どのようなデータを使ってどのような分析を行うべきかを考えます。統計的手法や機械学習モデルを用いてデータを分析し、有益な知見を抽出します。
また、分析結果をグラフや図表で可視化し、非専門家にもわかりやすく説明する能力も求められます。顧客の購買傾向分析や需要予測、不良品発生要因の特定など、具体的なビジネス成果につながる分析を実施します。
必要とされるスキルと専門知識
データエンジニアリングに必要なスキルは、システム開発やデータベース技術が中心です。プログラミング言語の知識、データベース管理システムの操作、クラウドサービスの活用などの技術力が求められます。また、大量のデータを効率的に処理するための並列処理技術や、データの圧縮技術なども重要です。
システム全体のアーキテクチャを設計する能力や、障害発生時に迅速に対応できるトラブルシューティング能力も必要です。さらに、データのセキュリティやプライバシー保護に関する知識も欠かせません。技術的な深い知識と、安定したシステムを構築する実践力が求められる分野です。
一方、データサイエンスに必要なスキルは、統計学や機械学習の知識が中心です。データの特性を理解し、適切な分析手法を選択できる能力が求められます。また、ビジネス課題を理解し、分析結果をビジネス価値に変換するためのコミュニケーション能力も重要です。プログラミングスキルも必要ですが、データエンジニアリングほど高度なシステム構築能力は求められません。むしろ、数学的思考力や論理的思考力、そして分析結果を説明するプレゼンテーション能力が重視されます。
成果物と評価指標
データエンジニアリングの成果物は、データ基盤そのものです。安定して稼働するデータパイプライン、高速にアクセスできるデータベース、信頼性の高いデータ処理システムなどが評価の対象となります。評価指標としては、システムの稼働率、データ処理速度、データの正確性、障害発生時の復旧時間などが挙げられます。
データエンジニアの仕事は、目立ちにくい裏方的な役割ですが、組織のデータ活用を支える重要な基盤を提供しています。システムが安定して動作し、データサイエンティストや分析担当者がストレスなくデータを活用できる環境を整えることが、データエンジニアの成果といえます。
一方、データサイエンスの成果物は、分析レポートや予測モデル、意思決定のための推奨事項などです。ビジネス課題の解決につながる具体的な提案や、将来予測の精度などが評価の対象となります。評価指標としては、予測精度、分析から得られた知見の有用性、提案の実行による売上向上やコスト削減などの経営成果が挙げられます。データサイエンスは、直接的にビジネス価値を生み出すことが期待される分野です。
業務における視点と思考方法
データエンジニアリングの視点は、技術的な最適化と安定性に向けられています。どうすれば効率的にデータを処理できるか、どうすればシステムの信頼性を高められるかといった技術的な課題に焦点を当てます。また、将来的なデータ量の増加を見越した拡張性や、コスト効率も重要な考慮事項です。
データエンジニアは、システム全体を俯瞰し、各コンポーネントが円滑に連携する仕組みを設計します。障害が発生した場合の影響範囲を最小限にする設計や、バックアップ体制の構築など、リスク管理の視点も持っています。
一方、データサイエンスの視点は、ビジネス価値の創出に向けられています。データから何を読み取れるか、どのような知見がビジネスに役立つかという問いに答えることが求められます。データサイエンティストは、データの背後にある意味やパターンを探求し、それをビジネス課題の解決につなげる思考を持っています。また、分析結果の信頼性や妥当性を検証し、誤った結論を導かないよう注意を払います。
データエンジニアリングとデータサイエンスの関係性とは
データエンジニアリングとデータサイエンスは、互いに補完し合う密接な関係にあります。データサイエンスがその力を発揮するためには、質の高いデータが整備されている必要があり、それを実現するのがデータエンジニアリングの役割です。
データエンジニアが構築したデータ基盤の上で、データサイエンティストは分析を行います。もしデータが散在していたり、品質が低かったりすると、データサイエンティストは分析作業よりもデータの整理に多くの時間を費やすことになり、本来の分析業務に集中できません。
逆に、データサイエンティストからのフィードバックは、データエンジニアリングの改善に役立ちます。どのようなデータが必要か、どのような形式が分析しやすいかといった要求を受けて、データエンジニアはシステムを最適化していきます。このように、両者は協力し合うことで、組織のデータ活用を最大化することができます。
また、大規模なデータプロジェクトでは、両者の役割分担が明確であることが成功の鍵となります。データエンジニアが安定したデータ基盤を提供し、データサイエンティストがその上で高度な分析を行うという連携によって、データから最大の価値を引き出すことができるのです。
それぞれが活躍する分野
データエンジニアリングとデータサイエンスは、それぞれ異なる場面で活躍しています。ここでは具体的な活躍分野をご紹介します。
・データエンジニアリングが活躍する場面
・データサイエンスが活躍する場面
・両者が協力して成果を出す場面
・今後の発展が期待される分野
データエンジニアリングが活躍する場面
データエンジニアリングは、大量のデータを扱う必要がある場面で特に重要な役割を果たします。リアルタイム性が求められるシステムや、複数のデータソースを統合する必要がある場合に、データエンジニアの専門性が発揮されます。
たとえば、製造業の生産管理システムでは、工場内の多数のセンサーから常時データが送られてきます。これらのデータをリアルタイムで収集し、異常を検知する仕組みを構築するには、高度なデータエンジニアリング技術が必要です。また、在庫管理や物流最適化など、複数のシステムからデータを集約して統合的に管理する場合も、データエンジニアリングの出番です。
さらに、金融業界での取引データ処理や、インターネットサービスでのユーザー行動ログの収集など、秒単位で膨大なデータが発生する環境では、効率的なデータ処理基盤が不可欠です。データエンジニアは、このような高負荷環境でも安定して動作するシステムを設計し、運用します。データの信頼性と可用性を保証することが、データエンジニアリングの重要な使命です。
データサイエンスが活躍する場面
データサイエンスは、データから知見を得て意思決定に活かす場面で力を発揮します。ビジネス戦略の立案や、顧客行動の理解、市場トレンドの予測など、データに基づいた判断が求められる場面で活躍します。
たとえば、小売業での需要予測では、過去の販売実績や季節変動、天候、イベントなどの情報を総合的に分析して、将来の需要を予測します。これにより、適切な在庫量を維持し、機会損失や過剰在庫を防ぐことができます。また、顧客の購買傾向を分析して、効果的なマーケティング施策を提案することもデータサイエンスの重要な役割です。
医療分野では、患者データから病気のリスク因子を特定したり、治療効果を予測したりする研究が進められています。また、製造業では、品質データから不良品発生の要因を分析し、改善策を提案します。このように、データサイエンスは、データの背後に隠れたパターンや因果関係を明らかにし、実用的な知見を提供することで、さまざまな分野で価値を生み出しています。
両者が協力して成果を出す場面
データエンジニアリングとデータサイエンスが協力することで、より大きな成果を生み出せる場面も多くあります。特に、継続的にデータを収集し分析する必要がある場合や、分析結果を実際のシステムに組み込む場合には、両者の緊密な連携が不可欠です。
たとえば、推奨システムの構築では、データエンジニアがユーザーの行動ログを収集するシステムを構築し、データサイエンティストがそのデータから推奨アルゴリズムを開発します。さらに、開発されたモデルを本番環境に組み込み、リアルタイムで推奨を提供する仕組みを構築する際には、再びデータエンジニアの技術が必要になります。
また、異常検知システムでは、データエンジニアがセンサーデータを収集する基盤を構築し、データサイエンティストが正常と異常を判別するモデルを開発します。そして、そのモデルを実際の監視システムに統合し、アラートを発する仕組みを作るには、両者の協力が必要です。このように、エンドツーエンドでデータ活用を実現するためには、両者の専門性を組み合わせることが重要です。
今後の発展が期待される分野
今後、データエンジニアリングとデータサイエンスの重要性は、さらに高まっていくと考えられます。特に、AI技術の発展に伴い、大量の学習データを効率的に管理し、高度な分析を行う必要性が増しています。
自動運転技術の開発では、膨大な走行データを収集し、それを用いてAIモデルを訓練する必要があります。このプロセスでは、データエンジニアリングによる大規模データ基盤の構築と、データサイエンスによる高度なモデル開発の両方が不可欠です。また、スマートシティの実現に向けても、都市全体のセンサーデータを統合管理し、交通最適化やエネルギー管理に活用する取り組みが進んでいます。
さらに、個人情報保護の重要性が高まる中で、プライバシーを守りながらデータを活用する技術の開発も求められています。データエンジニアリングとデータサイエンスが協力して、安全で有益なデータ活用の仕組みを構築していくことが、今後ますます重要になっていくでしょう。
まとめ
データエンジニアリングとデータサイエンスは、どちらもデータを扱う専門分野ですが、その役割と目的は明確に異なります。データエンジニアリングはデータ基盤を構築し、データサイエンスはそのデータから価値ある知見を引き出します。
両者は互いに補完し合う関係にあり、協力することで組織のデータ活用を最大化できます。それぞれの専門性を理解し、適切に役割分担することが、データ駆動型ビジネスを成功させる鍵となります。今後もデータの重要性は増していくため、両分野の人材育成と協力体制の構築に取り組んでいきましょう。